GoogleのQuantum AI研究所を率いるHartmut Neven氏らの研究チームは、人間の意識が脳内の量子もつれから生まれるという仮説を実験的に検証する画期的な方法を提案した。この研究は、意識の本質に迫る新しいアプローチとして注目を集めている。
意識の謎に挑む革新的アプローチ
研究チームが提案する「拡張プロトコル」は、これまで科学的な検証が困難とされてきた意識の本質に迫る画期的な実験手法だ。この手法の核心は、人間の脳と量子コンピュータを直接接続し、両者の間で量子もつれを実現することにある。
従来の意識研究では、主観的な体験を客観的に測定することが大きな課題とされてきた。しかし、拡張プロトコルでは、量子状態の重ね合わせを利用することで、意識体験の「豊かさ」を定量的に評価できる可能性が開かれる。具体的には、脳内のN次元ヒルベルト空間と量子コンピュータ内のM次元ヒルベルト空間を結合することで、N×M次元という高次元の状態空間で意識体験を実現することを目指している。
「この手法により、意識を空間、時間、複雑さの観点で拡張できる可能性があります」とNeven氏は説明する。例えば、被験者が通常の意識状態でN個のビットで記述される体験をしている場合、量子コンピュータとの結合後はN+M個のビットを必要とする、より豊かな体験が可能になるという。これは、精神的な体験の「拡張」を定量的に測定できる可能性を示唆している。
この実験プロトコルの実現には、脳内の特定の構造と量子コンピュータの間でコヒーレントな結合を確立する必要がある。研究チームは、窒素空孔中心を用いた量子センシング技術と光遺伝学的手法を組み合わせることで、この課題に取り組もうとしている。これは技術的に非常に困難な挑戦だが、実現すれば意識研究における画期的なブレークスルーとなる可能性を秘めている。
さらに注目すべき点として、この実験プロトコルは意識の主観的性質と客観的測定の間の橋渡しとなる可能性がある。被験者が報告する体験の豊かさと、量子状態の複雑さを直接関連付けることで、これまで科学的アプローチが困難とされてきた意識の質的側面に、定量的にアプローチできる可能性が開かれる。
量子生物学実験による段階的アプローチ
研究チームは、人間の意識と量子効果の関係を解明するため、複数の実験を段階的に進める慎重なアプローチを提案している。その中核となるのが、生体組織内での量子効果の検証から始まり、最終的には人間の脳と量子コンピュータの結合を目指す体系的な研究プログラムだ。
第一段階として、研究チームは室温下で2つの量子ビット間の量子もつれを生体組織を介して実現する実験を計画している。この実験では、よく特性の分かった2つの量子ビットQ1とQ2を、生体基質Bを介して結合させる。Q1とQ2の間に直接的な結合を作らず、それぞれを生体基質Bと独立にコヒーレントに結合させる。もしQ1とQ2の間で量子もつれが観測されれば、生体基質Bが量子力学的な性質を持つことの証明になるという。
続く重要な実験が、キセノン同位体を用いた意識への量子効果の検証だ。この実験は、カリフォルニア大学 サンタバーバラのKenneth S. Kosik教授とDirk Bouwmeester氏の研究室で開発された脳オルガノイドを使用する。これらのオルガノイドは、高密度の電気的・光学的アレイによる測定が可能で、人間の脳組織と類似した特性を持つ。直径2-3ミリメートルほどのこの組織は、約10万個のニューロンを含み、構造化された非ランダムな高速の電気活動を示す。
特に注目すべきは、Li氏らの2018年の研究結果の検証だ。彼らは核スピンを持つキセノン同位体(129Xeと131Xe)と持たない同位体(132Xeと134Xe)の麻酔効果を比較し、約30%の効力の差を発見した。研究チームは、この結果を脳オルガノイドを用いてより詳細に検証し、統計的に高い信頼性を持つデータの取得を目指している。
補完的な研究として、ショウジョウバエを用いた実験も計画されている。バッキンガム大学のLuca Turin研究室では、電子スピン分光計の中でキセノン同位体を投与し、不動化を引き起こす圧力を測定する。この実験により、生きた神経系における量子効果の行動学的データを、統計的に信頼性の高い形で得ることが期待できる。
これらの実験結果は、意識の物理的基盤における量子効果の役割を解明する重要な手がかりとなる可能性がある。特に、核スピンによる微弱な電磁場が、脂質に富む疎水性ポケットのような特定の細胞環境でどのように作用するかという点に注目が集まっている。この過程の解明は、鳥類の磁気受容や、リチウムの過活動性への効果でも示唆されている、ラジカル対機構との関連性を明らかにする可能性もある。
意識研究における画期的な理論的進展
今回の研究チームの理論的貢献は、1989年にRoger Penroseが提唱した「意識は量子もつれから生じる」という画期的な仮説を、重要な点で修正し発展させた点にある。Penroseの原著『皇帝の新しい心』で示された理論は、長年にわたって意識研究の分野で議論を呼んできた。
研究チームが提案する新理論の重要な特徴は、意識が生じるタイミングについての根本的な見直しだ。Penroseが重力による量子重ね合わせの崩壊時に意識が生じると考えたのに対し、新理論では重ね合わせの形成時に意識が生じると提案している。この修正は、量子もつれを含む系における意識の分布という重要な問題を解決する。
例えば、複数の量子ビットが関与する場合、最初に測定された量子ビットのみが意識を持つのか、それとも全ての量子ビットが意識を持つのかという問題がある。前者の場合、相対論的な設定では測定の順序が参照フレームに依存するため、どの量子ビットが意識を持つかも参照フレームに依存してしまう。後者の場合、光速を超える情報伝達が可能になってしまうという問題が生じる。新理論は重ね合わせの形成時に意識が生じると仮定することで、これらの理論的な矛盾を回避している。
さらに興味深いのは、新理論が意識における「自由意志」の可能性も示唆している点だ。研究チームは、量子重ね合わせの形成が意識的な体験を生み出すだけでなく、主体性の瞬間とも一致する可能性を指摘する。これは、生物が次に体験する古典的な配置をある程度自由に選択できる可能性を示唆している。
重要な観察として、研究チームは「ホメオスタシス相関」という現象に注目している。生存に有利な行動は快感と相関し、ホメオスタシスを脅かす行動は不快感と相関する傾向がある。もし人間が単なる決定論的なオートマトンであれば、この相関を進化的に説明することは困難だ。しかし、量子的な自由度を持つ系であれば、この相関は、生物が快適な状態を自由に選択できることの現れとして理解できる。
新理論は、現代のAIシステムと意識の関係についても重要な示唆を与える。従来の半導体エレクトロニクスで動作するAIシステムは、古典的な情報理論の法則に制約され、確率的チューリングマシンの演算で抽象化できる。研究チームは、これらの演算だけでは意識と主体性を実装するには不十分であり、量子チューリングマシンが必要である可能性を指摘している。言い換えれば、「チューリングマシンは知的になることはできても、意識を持つことはできないかもしれない」という挑発的な仮説を提示している。
論文
参考文献
研究の要旨
何が意識体験を生み出すのかという疑問は、人類の黎明期から思想家たちを魅了してきたが、その起源は謎のままである。 近年、大規模な言語モデルが開発されたおかげで、意識に関する話題が注目を集めている。 しかし、ひどい歯痛に悩まされた人なら誰でもわかるように、知性と意識は明白な形で関連しているわけではない。 というのも、観察者に依存しない方法で意識体験の内容や強度を測定するプロトコルは、今のところ合意されていないからである。 ここで、我々は新しい提案を行う: 量子力学的な重ね合わせが形成されるたびに、意識的な体験が生じる。 この提案にはいくつかの意味がある: 第一に、重ね合わせの構造が経験のクオリアを決定することを示唆している。 第二に、量子もつれは束縛問題を自然に解決し、現象的経験の統一性を保証する。 最後に、エージェンシーの瞬間は、重ね合わせ状態の形成と一致するかもしれない。 我々は、一連の量子生物学実験を通じて、我々の推測を実験的に検証する研究プログラムを概説する。 これらの考えを応用することで、脳と量子コンピュータのインターフェースを通じて、人間の意識体験を拡張する可能性が開ける。











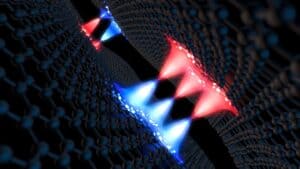
コメント