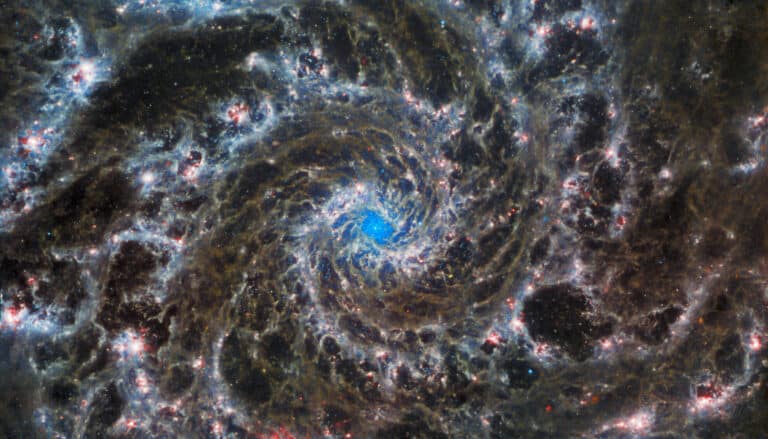宇宙が膨張していることは知られているが、その膨張速度を巡る測定値の矛盾、いわゆる「ハッブルテンション(ハッブル定数の緊張)」は現代宇宙論における最大の謎の一つである。この難問に対し、宇宙全体が非常にゆっくりと自転しているという新たなモデルが解決の糸口を示すかもしれない。ハワイ大学マノア校天文研究所のIstván Szapudi氏を含む研究チームが提唱するこの説は、物理学の根幹に関わる問題に一石を投じるものであり、私たちの宇宙観を大きく変える可能性を秘めている。
宇宙論の長年のパズル「ハッブルテンション」とは
宇宙が膨張していることは、1920年代のEdwin Hubbleによる観測以来、広く受け入れられている事実である。そして、その膨張の速さを示す指標が「ハッブル定数」と呼ばれる値だ。この定数は、宇宙の年齢や大きさ、遠方銀河までの距離、そして宇宙の加速膨張を引き起こすとされる謎のエネルギー「ダークエネルギー」の影響を理解する上で、極めて重要な役割を担っている。いわば、宇宙の基本的なスケールを決める「ものさし」のようなものだ。
しかし、このハッブル定数の測定方法には、大きく分けて二つの主要なアプローチがあり、それぞれが示す値が食い違うという問題が長年、宇宙論研究者を悩ませてきた。これが「ハッブルテンション」である。
1. 初期宇宙からのシグナル:宇宙マイクロ波背景放射 (CMB)
宇宙誕生から約38万年後に放たれた「宇宙最初の光」の名残であるCMBを観測する方法。プランク衛星などの精密な観測データに基づき、標準的な宇宙モデル(ΛCDMモデル:ラムダ・コールド・ダーク・マター・モデル)を仮定して計算すると、ハッブル定数は約67.4 km/s/Mpc(キロメートル毎秒毎メガパーセク)となる。1メガパーセクは約326万光年なので、これは326万光年離れた銀河が秒速約67.4kmの速度で遠ざかっていることを意味する。
2. 近傍宇宙の「ものさし」:標準光源
比較的近く(数十億光年以内)の宇宙にある、明るさが正確に分かっている天体(Ia型超新星やセファイド変光星など)を「標準光源」として利用する方法。これらの天体の見かけの明るさと真の明るさを比較することで距離を正確に測定し、後退速度と合わせてハッブル定数を求める。この方法では、約73.0 km/s/Mpcという値が得られている。
当初は観測誤差の範囲内と見られていたこの差は、近年の観測精度の向上により、統計的に極めて有意なレベル(5σ:標準偏差の5倍。偶然である確率が約350万分の1以下)に達している。これは、現在の標準宇宙モデルのどこかに見落としや誤りがある可能性を示唆しており、宇宙論の根幹を揺るがしかねない「危機」とも言える状況なのだ。まるで、安定しているはずのジェンガタワーの基礎ブロックが、実は少しずれていることが判明したようなものである。
新たな可能性:自転する宇宙モデル
この深刻なハッブルテンションを解決するために、ダークエネルギーの性質を変えたり、未知の素粒子を導入したりと、様々な理論的試みがなされてきた。そんな中、Szapudi氏らの研究チームは、全く新しい視点を提案した。それは、「宇宙全体が自転しているのではないか?」というアイデアだ。彼らの研究成果は、天文学誌『Monthly Notices of the Royal Astronomical Society』に掲載された論文で詳述されている。
研究チームは、まず標準的な宇宙モデル(ΛCDMモデル)に基づきつつ、宇宙を満たす物質とエネルギーを「ダークフルード」と呼ばれる流体として扱う、簡略化された数学モデル(ニュートン近似を用いたオイラー・ポアソン方程式系)を構築した。そして、このモデルに「ごくわずかな宇宙全体の回転」を導入してみたのである。
Szapudi氏は、「古代ギリシャの哲学者ヘラクレイトスの有名な言葉『Panta Rhei(万物は流転する)』に倣い、我々は『Panta Kykloutai(万物は回転する)』ではないかと考えました」と語る。地球も太陽も、そして我々の天の川銀河さえも回転している。ならば、宇宙全体が回転していても不思議ではない、という発想だ。
驚くべきことに、このわずかな回転を加えたモデルは、ハッブルテンションを見事に緩和させる結果を示した。論文によれば、宇宙が約5000億年かけて1回転する程度の極めて遅い角速度(ω₀ ≈ 2 × 10⁻³ Gyr⁻¹)で自転していると仮定すると、初期宇宙(CMB)の観測データと整合性を保ちつつ、近傍宇宙(標準光源)で測定される高いハッブル定数(約73 km/s/Mpc)を再現できるというのだ。
なぜ回転が矛盾を解決するのか? 研究チームのモデルでは、宇宙の回転の効果は、観測者からの距離が遠くなるほど顕著になる。つまり、CMBのような非常に遠方からのシグナル(初期宇宙)と、標準光源のような比較的近傍のシグナルとでは、回転の影響の受け方が異なるため、見かけ上の膨張率に差が生じる、と説明される。遠近で異なる「ゆがみ」が、測定値のずれを生んでいた、というわけだ。
自転モデルの妥当性と興味深い論点
宇宙が自転している、というアイデア自体は突飛に聞こえるかもしれないが、全く根拠がないわけではない。
- 物理法則との整合性: このモデルで必要とされる回転速度は、現在の物理法則(特にアインシュタインの一般相対性理論)と矛盾しない範囲に収まっている。特に懸念されるのは、高速な回転によって時空が歪み、過去へのタイムトラベルが可能になる「閉じた時間的ループ(CTC)」の形成だが、今回のモデルで示された回転速度は、観測可能な宇宙の地平線において物質の速度が光速を超えない範囲であり、この問題を回避できる「最大許容回転速度」に近い値であることが示唆されている。
- 過去の観測的示唆?: 近年、遠方宇宙の銀河の回転方向(スピン)に、特定の向きを好む偏りが見られる、という観測報告もある。もし宇宙全体が一様な状態(非回転)であれば、銀河のスピン方向はほぼ半々になるはずであり、この偏りが宇宙規模の回転と関連している可能性も指摘されているが、まだ決定的な証拠とは言えない。
- 回転の原因は?: もし宇宙が本当に自転しているとしたら、何がその回転を引き起こしたのだろうか? これは非常に興味深く、そして難しい問いである。一つの奇抜な仮説として、我々の宇宙が、別の親宇宙に存在する巨大なブラックホールの内部にあるのではないか、というものがある。ブラックホール自体が高速で回転する天体であることから類推されるアイデアだが、これはあくまで推測の域を出ない。
- モデルの限界: 今回の研究は、重要な第一歩ではあるが、いくつかの注意点もある。用いられたモデルは、計算を単純化するためにニュートン力学の近似を用いており、厳密な一般相対論的扱いではない。また、「ダークフルード」という概念自体も、標準的なΛCDMモデルとは異なる、まだ主流とは言えないアイデアに基づいている。
今後の展望と研究の意義
Szapudi氏らのチームは、今回の初期的な結果を踏まえ、今後はより現実に近い、回転する宇宙の完全なコンピューターモデルを構築することを目指している。これにより、この理論が予測する具体的な観測的証拠(例えば、CMBの温度ゆらぎの特定のパターンや、遠方銀河の分布に見られる微細な異方性など)を特定し、実際の天文観測データと比較することで、宇宙の自転仮説を検証することが可能になると期待される。
もし、今後の研究によって宇宙の自転が確かなものとなれば、それはハッブルテンションの解決に留まらず、宇宙の成り立ちや進化、そして物理法則そのものに対する我々の理解を根本から覆す、まさに革命的な発見となるだろう。
まだ多くの検証が必要な段階ではあるが、「宇宙は回っているのかもしれない」というこの大胆な問いかけは、宇宙の謎を探求する新たな扉を開いたと言えるだろう。
論文
- Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Can rotation solve the Hubble Puzzle?
参考文献
- University of Hawaii: UH astronomer finds the universe could be spinning