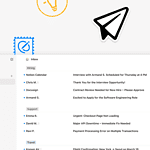日本の公正取引委員会(以下、公取委)は2025年4月15日、米Googleに対し、独占禁止法に違反する行為があったとして排除措置命令を出した。対象となったのは、Androidスマートフォンにおける検索サービスに関する契約慣行である。巨大IT企業「GAFAM」の一角であるGoogleに対し、公取委が排除措置命令を出すのは今回が初めてであり、国内外で注目が集まっている。
何が問題とされたのか?公取委が指摘したGoogleの「不公正な取引方法」
公取委が問題視したのは、GoogleがAndroidスマートフォンメーカーや移動通信事業者との間で結んでいた二種類の契約、「本件許諾契約」と「本件収益分配契約」における特定の条件である。これらの契約を通じて、Googleは自社の検索サービスの優位性を不当に維持・強化し、競合他社の事業活動を制限していたと認定された。
1. 「Google Play」利用の条件としての抱き合わせ(本件許諾契約)
Androidスマートフォンにとって、アプリストア「Google Play」は必要不可欠な存在だ。これがなければ、ユーザーは多種多様なアプリを簡単に入手できず、スマホの商品価値は著しく低下する。公取委によれば、Googleはこの「Google Play」のプリインストール(スマートフォンへの初期搭載)をメーカーに許諾する条件として、以下の2点を要求していた。
- Google検索アプリとChromeブラウザのプリインストール: Googleの検索アプリ(「Google Search」)とそのウィジェット(ホーム画面に置かれる検索窓など)、さらにウェブブラウザ「Google Chrome」を必ずプリインストールすること。
- 初期ホーム画面への配置: 上記アプリのアイコン(フォルダ格納含む)やウィジェットを、ユーザーが最初に目にする「初期ホーム画面」の目立つ位置に配置すること。
これにより、ユーザーは購入時からGoogleの検索サービスに触れる機会が多くなり、他の検索サービスを選択する可能性が低くなる。これは、競争上極めて有利な状況をGoogleにもたらすものだ。
2. 収益分配と引き換えの競合排除(本件収益分配契約)
Googleは、自社の検索サービス(Google検索やChromeブラウザ経由)で行われた検索に伴って表示される検索広告から収益を得ている。そして、その収益の一部を、「本件収益分配契約」(Google Mobile Revenue Share Agreement, Google Mobile Incentive Agreement等と題される契約)に基づき、特定のスマホメーカーや移動通信事業者に分配していた。
問題は、この収益分配の「条件」として、競合他社を排除するような要求が行われていた点にある。公取委が認定した主な条件は以下の通りだ。
- 競合検索機能の実装禁止: 他の一般検索サービス事業者(例:Yahoo! Japanなど)の検索アプリやウィジェット、検索機能への接続を主目的とする機能(例:特定の検索サービスを呼び出すボタンなど)をスマートフォンに実装しないこと、させないこと。
- 競合検索機能の紹介・推奨禁止: 利用者に対し、他の検索サービスを紹介したり、利用を勧めたりしないこと。
- Google検索のデフォルト化: スマートフォン上の全ての検索機能について、利用される検索サービスをGoogleの一般検索サービスとすること。
- Chromeのデフォルト化と設定維持:
- 既定のブラウザ(ユーザーがリンクを開いた際に自動で起動するブラウザ)を「Google Chrome」とすること。
- Chromeのアイコンをホーム画面下部のドック(常に表示される領域)に配置すること。
- Chromeの検索設定(アドレスバーでの検索時に利用する検索エンジンなど)を、Googleの検索サービスが選択された状態から変更しないこと、させないこと。
- 上記設定の変更を利用者に促したり、提案したりしないこと。
- 他のブラウザの検索設定制限: Chrome以外のブラウザを搭載する場合でも、その検索設定をGoogleの検索サービスまたは移動通信事業者のホームページを指定する設定とすること。
これらの条件は、メーカーや通信事業者が他の検索サービスを採用するインセンティブを奪い、Google検索への依存を強いるものだ。特に、収益分配という経済的利益と引き換えに競合排除を求める行為は、独占禁止法上の「不公正な取引方法」の中の「拘束条件付取引」(相手方の事業活動を不当に拘束する条件をつけて取引すること)に該当すると判断された。
公取委は、これらの行為が遅くとも2020年(令和2年)7月以降に行われ、日本のAndroidスマートフォン市場における公正な競争を阻害していると結論付けた。調査によれば、2023年12月時点でメーカー6社と契約があり、国内で販売されるAndroidスマホの少なくとも8割以上が対象になっていたという。また、公取委の命令書によると、2023年に国内で販売されたAndroidスマホの少なくとも8割は本件許諾契約の対象であり、Google検索機能が実装されていた。さらに、2024年7月時点で、本件収益分配契約の対象となったスマホの台数は、国内で利用されている特定Androidスマホの過半数を占めていた。これは、Googleの契約慣行が市場全体に広範な影響を与えていたことを示唆している。
なぜ「排除措置命令」なのか?過去の対応との違い
公取委が巨大IT企業に対して措置を講じるのはこれが初めてではない。例えば、2023年4月には、GoogleがLINEヤフー(当時ヤフー)との検索広告に関する提携において、ヤフーのモバイル向け広告配信技術の利用を制限した疑いについて、「確約手続」に基づきGoogleが提出した改善計画を認定している。
確約手続とは、公取委が違反の「疑い」を指摘し、事業者が自主的に問題解消のための計画を提案、公取委がそれを認定すれば、違反認定や排除措置命令を出さずに手続きを終了させる制度だ。迅速な問題解決が期待できる一方、違反の有無が法的に確定されないという側面もある。
しかし今回は、確約手続ではなく、より重い行政処分である「排除措置命令」が下された。これは、公取委がGoogleの行為を単なる「疑い」ではなく、明確な「独占禁止法違反」と認定したことを意味する。これは、審査開始から1年以上が経過し、違反事実の認定が進んでいたことなどが、命令に踏み切った背景にあるとみられる。公取委幹部は「証拠がそろっているのだから命令を出すときには出すという姿勢を示すことが企業側の自主的な改善の機運を生むことにつながる」と語っており、巨大IT企業に対してより厳格な姿勢で臨むというメッセージとも受け取れる。
今回の命令は、Googleに対し、以下の点を求めている。
- 違反行為の取りやめ: 上記で指摘された契約条件の要求を取りやめること。
- 取締役会等での決議: 違反行為を取りやめること、及び今後同様の行為を行わないことを、業務執行の決定機関(取締役会など)で決議すること。
- 関係者への通知・周知徹底: 命令に基づいて採った措置を、関係するスマホメーカーや移動通信事業者に通知し、自社の役員や従業員、子会社の役員・従業員にも周知徹底すること。
- 将来の禁止行為: 今後、同様の違反行為(Google Playの許諾と抱き合わせで検索関連アプリの搭載・配置を求めること、収益分配等を条件に競合検索サービスの排除や自社サービスのデフォルト化・設定維持等を求めること)を行わないこと。
- 再発防止策:
- 独占禁止法遵守のための行動指針を作成し、役員・従業員に周知徹底すること。
- 定期的な研修及び監査を実施すること。
- 第三者による監視: 独立した第三者を選定し、命令後5年間、措置の履行状況を監視させ、その状況を公取委に報告させること。
特に、5年間にわたる第三者監視は、命令の実効性を担保するための異例の措置であり、公取委の本気度、Googleに対する監視の厳しさを示している。
市場と利用者への影響は?Androidスマホは変わるのか?
今回の排除措置命令は、日本のスマートフォン市場、特に検索サービス分野にどのような影響を与えるのだろうか。
1. スマートフォンメーカー・通信事業者の選択肢拡大
まず考えられるのは、メーカーや通信事業者の自由度が高まることだ。これまではGoogle Playを利用するために、あるいは収益分配を得るために、半ば強制的にGoogle検索やChromeをプリインストールし、有利な位置に配置する必要があった。また、競合検索サービスの採用も制限されていた。
命令によりこれらの拘束がなくなれば、メーカーは理論上、
- Google以外の検索アプリ(例:Yahoo!検索、Microsoft Bing、DuckDuckGoなど)をプリインストールする。
- 複数の検索ウィジェットを初期ホーム画面に配置する。
- デフォルトの検索エンジンやブラウザを自由に選択する(あるいは利用者に選択させる)。
といったことが可能になる。これにより、メーカーは端末の差別化を図りやすくなるかもしれない。
ただし、スマホメーカーの担当者がNHKの取材で語っているように、「端末メーカーが競争力を維持できているのは、GoogleがOSやアプリなどを無償で提供しているからだ」という現実もある。Googleとの関係性を考慮し、実際には大きな変更を加えない可能性も否定できない。とはいえ、交渉力は以前より高まるだろう。
2. 検索サービス市場の競争促進
Google以外の検索事業者にとっては、Androidスマートフォンという巨大なプラットフォーム上で自社サービスを展開する機会が拡大する。これまでプリインストールやデフォルト設定の壁に阻まれてきた競合サービスが、メーカーとの提携などを通じてユーザーにリーチしやすくなる可能性がある。
総務省の調査によれば、2023年1月時点で、日本のスマートフォン検索サービスにおけるGoogleのシェアは約81%と圧倒的であり、ヤフーは約16%にとどまる。この寡占状態が緩和され、健全な競争が促進されることが期待される。競争が活発になれば、検索技術の革新やサービス改善が進む可能性もある。
3. 利用者への影響
利用者にとっては、スマートフォンの初期設定で表示される検索サービスやブラウザの選択肢が増える可能性がある。また、メーカーが独自の判断で複数の検索サービスを提供したり、より自由なカスタマイズを許容したりすれば、利便性が向上するかもしれない。
しかし、短期的には大きな変化を感じにくいかもしれない。多くのユーザーはデフォルト設定のまま利用する傾向があり、メーカー側も急激な変更は避ける可能性があるからだ。むしろ、選択肢が増えることで混乱を感じるユーザーもいるかもしれない。長期的に競争が促進されれば、より良いサービスが生まれるという形で恩恵を受ける可能性はある。
4. Googleのビジネス戦略への影響
Googleにとって、検索トラフィックの確保は広告収益の根幹であり、モバイル検索はその中でも極めて重要だ。今回の命令は、Androidエコシステムにおける検索サービスのデフォルト地位を確保するための重要な手段(契約による囲い込み)に制約を加えるものである。
Googleは「日本のスマートフォンメーカーや通信事業者は、Googleとの取り引きを強制されていません。…自らGoogleを選択している」と主張し、命令に遺憾の意を示している。今後、命令の内容を精査し、対応を決定するとしているが、収益分配モデルの見直しや、メーカーとの新たな関係構築が必要になる可能性がある。技術革新やサービス改善によって、契約に頼らずとも選ばれる存在であり続けることが、より一層求められるだろう。
国内外の規制トレンドと今後の焦点
今回の公取委の動きは、世界的な巨大IT企業への規制強化の流れと軌を一にするものだ。
- 日本: 2024年には「スマホソフトウエア競争促進法」が本格施行される予定だ。この法律は、アプリストアや検索エンジンなどで支配的な地位にある事業者(GoogleやAppleなどが想定されている)に対し、他社ストアの提供妨害の禁止、他社決済システムの利用妨害の禁止、検索結果での自社サービス優遇の禁止などを定める。違反した場合、国内売上高の20%(繰り返しの場合は30%)という高額な課徴金が科される可能性があり、今回の独禁法に基づく命令よりもさらに強力な規制となる。
- EU: デジタル市場法(DMA)が2023年から本格運用され、Googleを含む大手プラットフォーマーに対し、様々な義務を課している。違反時の制裁金は世界売上高の最大10%(繰り返しで20%)と非常に高額だ。EUはすでにGoogleに対し、DMA違反の疑いで調査を進めている。
- 米国: 司法省がGoogleに対し、検索および検索広告市場での反トラスト法(独占禁止法)違反で提訴しており、裁判所は一部訴えを認めている。司法省は是正策として、Chromeブラウザ事業の売却などを求めている。
このように、各国でプラットフォームの「門番」としての力を利用した競争阻害行為に対する監視の目は厳しくなっている。
今後の焦点は、Googleが排除措置命令を誠実に履行するかどうか、そして第三者による監視が実効性を持つかである。また、スマホメーカーや競合事業者がこの変化をどう捉え、行動に移すかによって、市場が実際に変わるかどうかが決まる。
今回の公取委の命令は、日本のデジタル市場における公正な競争環境の確保に向けた重要な一歩である。長年この業界を見てきた者として、これが単なる一過性の措置に終わらず、イノベーションを促進し、最終的に利用者の利益につながる変化を生み出すことを期待したい。市場の動向を引き続き注視していく必要がある。
Source