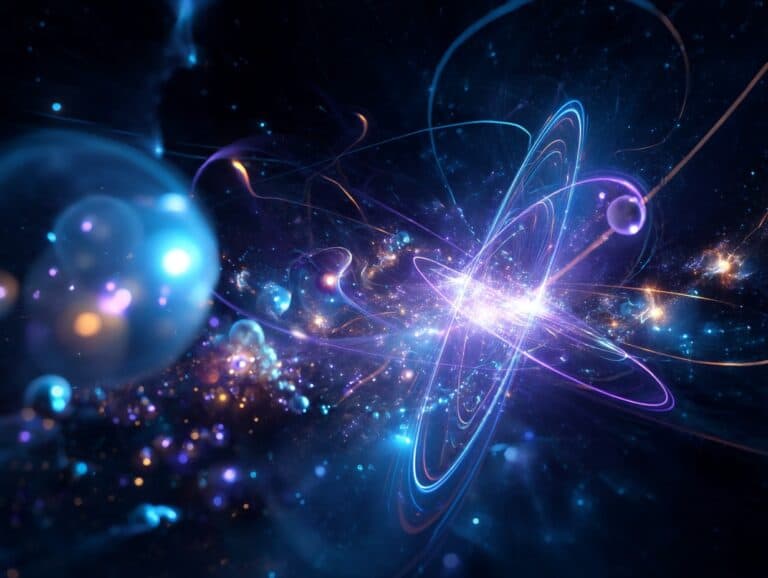マサチューセッツ工科大学(MIT)の研究者チームが、物理的なケーブル接続なしに複数の量子プロセッサ間で直接情報を伝達する画期的なインターコネクト(相互接続)技術を開発した。マイクロ波光子(フォトン)を用いて量子ビット間の「リモートエンタングルメント」を生成するこの新手法は、将来のスケーラブルでエラー耐性の高い量子コンピュータ実現に向けた重要な一歩となる可能性がある。
量子コンピュータ開発の障壁:接続性とエラーの問題
量子コンピュータは、従来のスーパーコンピュータでは到底解けない複雑な問題を解決する可能性を秘めたものとして、その開発が進められているが、その実現には多くの技術的課題が存在する。特に、複数の量子プロセッサ(QPU)を効率的に接続し、量子情報をエラーなく共有するスケーラブルなアーキテクチャの構築は大きなハードルとなっている。
現在主流の量子コンピュータシステムでは、個々のQPU間の接続は限定的であり、「ポイント・ツー・ポイント」接続と呼ばれる方式に依存していることが多い。この方式では、情報が目的地に到達するまでに複数のノード(中継点)を経由する必要があり、データ転送が鎖のように連なって行われる。しかし、この「ホップ」ごとに情報がノイズにさらされる危険性が高まり、計算エラーが発生する確率が増加するという問題があった。大規模な量子コンピュータを構築するには、接続数を増やしながらエラー率を低く抑える必要があるが、ポイント・ツー・ポイント接続では限界があった。
MITの新提案「オール・ツー・オール」接続への道
この課題を克服するため、MITの研究チームは、ネットワーク内の任意のプロセッサが他の中間ノードを経由せずに直接通信できる「オール・ツー・オール」接続を可能にする新しいインターコネクトデバイスを開発した。これにより、情報の伝達経路が簡素化され、エラーの蓄積を抑制し、より高速な通信が期待できる。
また、この技術は、スケーラビリティ(拡張性)の観点からも大きな利点を持つ。MITの新たなインターコネクトデバイスでは、理論上、必要なだけ多くの量子プロセッサモジュールを接続することが可能となり、大規模な分散型量子コンピュータネットワークの構築に道を開くものである。
技術の核心「マイクロ波フォトン」と「超伝導導波路」
この画期的なインターコネクト技術の中心にあるのは、マイクロ波フォトンと特殊な超伝導ワイヤーである。
研究チームは、まず情報を運ぶ粒子としてマイクロ波領域の光子、すなわちマイクロ波フォトンを採用した。そして、これらのフォトンがプロセッサ間を行き来するための「量子ハイウェイ」として機能する超伝導ワイヤー(導波路)を設計した。超伝導材料は極低温で電気抵抗がゼロになるため、情報の損失を最小限に抑えながらフォトンを伝送できる。
実験では、この導波路に2つの量子モジュールを接続した。各モジュールは、それぞれ4つの超伝導量子ビット(Qubit)を含んでいる。量子ビットは量子情報の基本単位であり、ここでは導波路とより大きな量子プロセッサとの間のインターフェースとして機能する。具体的には、モジュール内の一部の量子ビットがマイクロ波フォトンを放出し、別の量子ビットがそれを受信・吸収する役割を担う。さらに、近くにあるデータ処理用の量子ビットに情報を転送する機能も持つ。
研究チームは、一連のマイクロ波パルスを特定の量子ビットに印加することで、エネルギーを与えてフォトンを放出させることに成功した。さらに、これらのパルスの位相(波のタイミング)を精密に制御することで、量子干渉効果を利用し、フォトンを導波路内の特定の方向(右向きまたは左向き)に選択的に放出させる「キラル(方向性のある)放出」を実現した。論文によれば、これは量子干渉を利用した「調整可能なキラル量子電磁力学(tunably chiral waveguide quantum electrodynamics)」の応用である。同様に、パルスの時間反転操作を行うことで、任意の距離にある別のモジュールの量子ビットが、特定の方向から来たフォトンを選択的に吸収することも可能にした。
MIT電子工学研究所(RLE)のWilliam D. Oliver教授は、「フォトンの『投球と捕球』により、非局所的な量子プロセッサ間に『量子インターコネクト』を作り出すことができ、それによってリモートエンタングルメントが可能になる」と説明している。
「半フォトン」によるリモートエンタングルメント生成の妙技
量子コンピュータの能力を最大限に引き出す鍵となる現象の一つが「量子もつれ(エンタングルメント)」であり、特に離れた場所にある量子ビット間のもつれは「リモートエンタングルメント」と呼ばれる。これは、2つの量子粒子が、どれだけ離れていても、あたかも一つのシステムであるかのように振る舞い、一方の状態を測定するともう一方の状態が瞬時に確定するという奇妙な相関関係である。量子もつれ状態にある量子ビット群は、古典コンピュータでは不可能な複雑なアルゴリズムの実行を可能にする。
しかし、単にフォトンをモジュール間で送受信するだけでは、リモートエンタングルメントは自動的に生成されない。量子もつれを生成するためには、より巧妙な仕掛けが必要となる。
研究チームは、フォトンを放出するためのマイクロ波パルスを、その持続時間のちょうど半分で停止させるという独創的な手法を考案した。量子力学的に言えば、これによりシステムは、フォトンが放出された状態と保持された状態の「重ね合わせ」という、奇妙な中間状態に置かれる。古典的なイメージで言えば、「半分のフォトン」が放出され、残りの半分が元のモジュールに保持されているような状態である。
この「半フォトン」が受信側モジュールに吸収されると、たとえ2つのモジュールが物理的に直接リンクされていなくても、それらの間にリモートエンタングルメントが形成される。実験では、この手法を用いて、2つのモジュールにまたがる4つのデータ量子ビット間で「W状態」と呼ばれる特定の多体エンタングルメント状態を生成することに成功した。
フォトン歪みへの挑戦と強化学習による最適化
フォトンが導波路を伝わる際には、導波路内の接続部やわずかな不整合などによって、フォトンの波形が歪んでしまうという問題が生じる。この歪みは、受信側モジュールでのフォトンの吸収効率を低下させ、結果的にエンタングルメント生成の成功率や忠実度(生成された量子状態が理想的な状態とどれだけ近いかを示す指標)を制限してしまう。
この課題に対処するため、研究チームは強化学習アルゴリズムを利用した。このAIアルゴリズムに、フォトンの吸収効率を最大化するように、放出・吸収プロトコルで用いるマイクロ波パルスの形状を最適化させたのである。具体的には、伝送中の歪みを見越して、送信前にあらかじめフォトンの波形を意図的に歪ませる「プレディストーション」を行った。
この最適化の結果、研究チームは60%を超えるフォトンの吸収効率を達成した。これは、生成された量子状態が確かに量子もつれ状態にあることを高い信頼性で証明するのに十分な値である。さらに詳細な測定により、生成された4量子ビットW状態の忠実度(Fidelity)は、左向きフォトン伝播の場合で62.4±1.6%、右向きフォトン伝播の場合で62.1±1.2%であることが確認された。これらの値は、エンタングルメントが存在するための閾値である50%を明確に上回っており、また、エンタングルメント蒸留(purification)と呼ばれるエラー訂正技術を適用可能なレベルにあることも示唆している。
論文の筆頭著者であるAziza Almanakly氏(電気工学・コンピュータ科学専攻の大学院生)は、「この研究における課題は、吸収効率を最大化するためにフォトンを適切に成形することでした」と述べている。
スケーラビリティと量子技術の未来への展望
今回開発されたインターコネクトアーキテクチャは、「オール・ツー・オール」接続をサポートする点が大きな特徴である。これは、単一の導波路に沿って複数のモジュールを配置し、その中から任意のペアを選んで直接通信させ、リモートエンタングルメントを生成できることを意味する。現在のポイント・ツー・ポイント接続の制約から解放され、より柔軟で拡張性の高い量子コンピュータネットワークの構築が可能になる。
研究チームは、今後の改善点として、フォトンが伝播する経路の最適化を挙げている。例えば、現在の別々のマイクロ波パッケージを接続する方式ではなく、モジュールを3次元的に集積することで、接続部分での損失をさらに低減できる可能性がある。また、プロトコル自体を高速化することで、エラーが蓄積する時間を短縮することも考えられる。論文の補足情報によれば、現在の損失の主な原因は、パッケージ間の接続や導波路内の散乱損失、データ量子ビットのデコヒーレンス(量子状態の消失)であり、これらは原理的に改善可能であると見積もられている。目標としては、吸収効率を90%以上に高めることも視野に入れている。
Almanakly氏は、「原理的には、我々のリモートエンタングルメント生成プロトコルは、他の種類の量子コンピュータや、より大きな量子インターネットシステムにも拡張可能です」と結論付けている。この技術は、超伝導量子ビットを用いたシステムだけでなく、他の方式の量子コンピュータ間の接続や、将来の量子情報通信ネットワークの基盤技術としても応用される可能性を秘めている。
Paper
Source