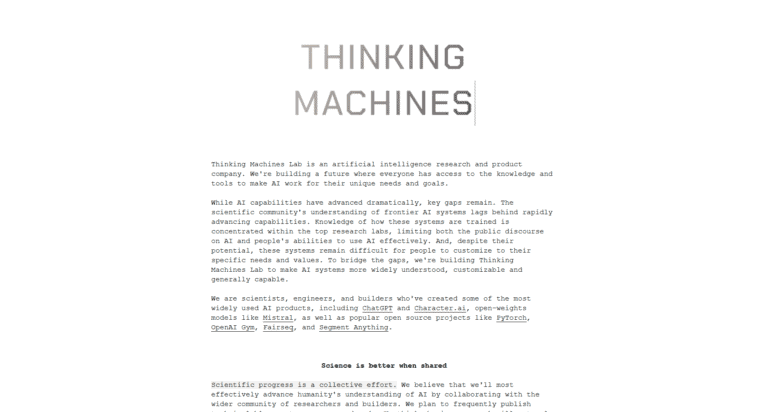OpenAIの元CTO、Mira Murati氏が設立した新たなAIスタートアップ「Thinking Machines Lab」が、業界の常識を覆す可能性のある動きを見せている。製品リリース前のシード段階にもかかわらず、20億ドル(約3,100億円)という巨額の資金調達を目指していると報じられたのだ。この動きは、同社への期待の高さと、AI開発競争の激化を物語っている。
異例ずくめの巨額シード資金調達
Business Insiderが報じたところによると、Thinking Machines Labは現在、シード資金調達ラウンドの目標額を当初の倍となる20億ドルに引き上げ、交渉を進めているという。この情報が事実であれば、テクノロジー業界史上でも最大級のシードラウンドとなる。
注目すべきはその規模感である:
- 目標調達額: 20億ドル
- 評価額: 少なくとも100億ドル(約1兆5,500億円)に達する可能性
- 以前の報道: 3月時点では10億ドル調達目標、評価額90億ドルと報じられていた
通常、シードラウンドは事業の黎明期、アイデアやプロトタイプを検証する段階で行われる資金調達であり、その規模は数百万ドルから数千万ドル程度が一般的である。それに対し、Thinking Machines Labが目指すとされる20億ドルという額は、すでに確立された事業を持つ企業のレイターステージの調達額にも匹敵、あるいはそれを上回るほどの巨額さだ。
この異例とも言える資金調達目標の背景には、フロンティアAIモデル(現在最も高性能なAIモデル)の開発に不可欠な、莫大な計算資源、すなわち高性能なコンピューティング・インフラの確保があると考えられる。最先端AIの開発には、膨大なデータセットとそれを高速処理するための強力なハードウェアが必須であり、そのコストは近年、高騰の一途を辿っている。
ただし、この資金調達はまだ進行中であり、最終的な条件は変わる可能性もある。現時点で、Thinking Machines Labは具体的な製品を発表しておらず、収益も上げていない。それでもなお、これほどの巨額資金が集まる可能性が囁かれるのは、一体なぜなのであろうか。
OpenAIからの独立と「ドリームチーム」の結成
Thinking Machines Labが投資家からこれほど熱い視線を集める最大の理由は、その設立者と集結した卓越した人材にあると言えるだろう。
CEOを務めるMira Murati氏は、OpenAIのCTOとして、社会現象を巻き起こした「ChatGPT」や、驚異的な画像生成能力を持つ「DALL-E」、さらにはプログラミング支援AI「Codex」といった革新的な製品の開発を指揮してきた輝かしい実績を持つ。彼女はOpenAIに6年間貢献した後、昨年10月に同社を後にした。
さらに、経営陣にはOpenAIの共同創業者の一人であるJohn Schulman氏がChief Scientistとして、そしてChatGPTの共同開発者であるBarret Zoph氏がCTOとして名を連ねる。まさに、現代AIの最前線を切り開いてきた頭脳が集結しているのだ。
そして最近、さらに強力なメンバーがアドバイザーとして加わったことが明らかになった。
- Bob McGrew氏: 元OpenAI Chief Research Officer。昨年9月までOpenAIの研究部門を率いていた人物である。
- Alec Radford氏: OpenAIの基盤技術であるGPT(Generative Pre-trained Transformer)に関する独創的な研究論文を発表した筆頭著者。ChatGPTの基礎となるGPTシリーズや、音声認識モデル「Whisper」、画像生成モデル「DALL-E」の開発にも深く関与した、OpenAIの技術革新におけるキーパーソンの一人である。
彼らは皆、現在のAIブームを牽引してきたOpenAIの中核を担ってきた、いわばレジェンド級の人物たちだ。これらトップクラスの研究者やエンジニアが数十人規模でThinking Machines Labに集結しているという事実。それこそが、同社の将来性に対する強い期待感を生み出し、巨額の資金調達を後押ししていると考えられるのだ。まさに、AI界の「ドリームチーム」と呼ぶにふさわしい布陣と言える。
Thinking Machines Labが目指すAIとは?
では、この豪華絢爛なチームは、一体どのようなAIを創り出そうとしているのであろうか。
Thinking Machines Labは、2月のブログ投稿などを通じて、自社の目指す方向性について、いくつかの興味深いヒントを示している。
- より理解しやすく、カスタマイズ可能で、汎用的なAI: 現在広く使われているAIシステムよりも、ユーザーがその仕組みや動作を理解しやすく、個々のニーズや目標に合わせて柔軟に調整でき、さらに幅広いタスクに対応できるような、次世代のAIの開発を目指しているようだ。
- マルチモーダルAIと高度な推論機能: テキストだけでなく、画像や音声など、複数の種類の情報を統合的に扱えるマルチモーダルな能力。そして、単なるパターン認識を超えた、論理的な思考や問題解決に近い高度な推論機能を備えたAIモデルの構築を計画している。
- 科学やプログラミング分野での最先端能力と適応性: 特定の専門分野、例えば科学研究やソフトウェア開発といった領域で、現状の最先端を超える能力を発揮することを目指しつつも、それに留まらず「人間の専門知識の全スペクトルに適応できるAI」を追求するとしている。これは、既存の特定タスクに特化したAIよりも、はるかに高い柔軟性を持つことを示唆する。
- カスタマイズの容易性: ユーザーがAIを自身の特定の目的やワークフローに合わせて、より簡単に調整できるようにすることに重点を置いている。画一的な応答になりがちな既存の大規模言語モデルとは一線を画す、パーソナライズされたAI体験の提供を目指している可能性もある。
- オープンソースへの貢献: 開発したソフトウェアの一部、特にAIの安全性や信頼性に関連する技術については、積極的にオープンソースコミュニティに還元していく方針を明らかにしている。「技術ブログ、論文、コードを頻繁に公開する予定」だという。
まだ具体的な製品ロードマップはベールに包まれたままであるが、彼らが掲げる「個々のユーザーへの適応性」や「オープン性」といった方針は、現在の巨大AI企業が提供するサービスとは異なる、新しいAIのあり方を示す可能性を秘めていると言えるだろう。
AI業界への影響と今後の展望
Thinking Machines Labの野心的な動きは、AI業界全体にいくつかの重要な波紋を広げている。
第一に、AI開発コストのさらなる高騰を印象付けている。まだ製品もないシード段階のスタートアップが、20億ドルもの資金を必要とする可能性があるという事実は、最先端AIの開発がいかに資本集約的な競争となっているかを改めて浮き彫りにする。
第二に、トップタレント獲得競争の激化である。Murati氏の下に、OpenAI出身のスター級の人材がこれだけ集結したことは、優秀なAI研究者やエンジニアの獲得が、企業の成功を左右する極めて重要なファクターであることを改めて示している。
第三に、OpenAIにとって強力な競合が出現する可能性である。かつてOpenAIの中核を担った才能たちが、異なるアプローチ(カスタマイズ性、オープンソース重視など)を掲げて独立したことは、将来的にAI業界の勢力図を塗り替える可能性を十分に含んでいる。
今後の最大の注目点は、まず正式な資金調達の発表がいつ、どのような形で行われるかであろう。そして、Thinking Machines Labが具体的にどのような技術を開発し、どのような製品やサービスとして社会に実装していくのか、その全貌が徐々に明らかになってくるはずである。特に、彼らが重視する「カスタマイズ性」や「オープンソース」戦略が、AIの利用や開発のあり方にどのような変革をもたらすのか、業界全体が固唾を飲んで見守っていくことになる。
Mira Murati氏率いるThinking Machines Labは、まだ航海を始めたばかりのスタートアップだが、その異例の資金調達計画と集結した才能は、AIの未来に大きなインパクトを与えるポテンシャルを十分に感じさせる。
Sources