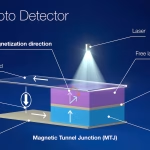Xiaomiがスマートフォンの心臓部である独自SoC(System on a Chip)開発を加速させるため、専門部署「チップ・プラットフォーム部」を新設し、その責任者にQualcomm出身の幹部を任命したことが明らかになった。。この動きは、スマートフォン市場でAppleやSamsungのように、ハードウェアからソフトウェアまで自社で一貫して開発・生産する「垂直統合」を目指すXiaomiの野心を示すものだ。
Qualcomm元幹部を迎え、チップ開発体制を強化
ITHomeの報道によると、Xiaomiは4月15日に社内で「チップ・プラットフォーム部」の設立を発表したという。この新部門は、スマートフォンの性能を左右する最も重要な部品であるSoCの自社開発を推進する役割を担う。
注目すべきは、この新部門の責任者に秦牧云(Qin Muyun)氏が就任した点だ。同氏は、長年モバイルチップ業界をリードしてきたQualcommで製品マーケティングのシニアディレクターを務めた経験を持つ人物だ。社内の体制は、秦氏がXiaomi CEOの雷軍(Lei Jun)氏に直接報告するようになっており、経営層がチップ開発の進捗を密接に監視する体制が敷かれている可能性があるという。Qualcommで豊富な経験を持つ人物をトップに据えたことは、XiaomiのSoC開発への本気度を物語っている。
この動きは、Xiaomiが自社開発SoCの発表を間近に控えているとされるタイミングで行われた点でも重要である。QualcommやMediaTekといった外部サプライヤーからのチップ調達は、最新技術を採用するほどコストが増大する傾向にある。Xiaomiは、チップの自社開発を進めることで、コスト管理の自由度を高め、サプライチェーンのリスクを低減し、長期的には製品の差別化を図る狙いがあると見られる。
長年の悲願、SoC自社開発への再挑戦
Xiaomiにとって、SoCの自社開発は長年の課題であった。同社は2017年に初の自社設計SoC「Surge S1」を発表している。TSMCの28nmプロセスで製造されたこのチップは、XiaomiをApple、Samsung、Huaweiに次いで自社SoCを持つスマートフォンメーカーの仲間入りさせたが、搭載された「Xiaomi 5C」が大きな成功を収めるには至らず、Surge S1の名も広く浸透するには至らなかった。
しかし、Xiaomiはチップ開発の夢を諦めたわけではなかった。Surge S1以降、同社はよりターゲットを絞ったチップ開発に注力してきた。ITHomeによると、近年、イメージング処理を担う「Surge Cシリーズ」、急速充電を制御する「Surge Pシリーズ」、バッテリー管理用の「Surge Gシリーズ」、通信信号を強化する「Surge Tシリーズ」、ディスプレイ表示を補助する「Surge Dシリーズ」など、特定の機能に特化した「小チップ」を次々と開発・投入し、着実にチップ設計能力と経験を蓄積してきたのだ。
これらの経験は、再び複雑なSoC開発に挑むための重要な布石であったと言えるだろう。
次世代SoCの姿:3nmか、それとも4nmか?
現在開発が進められているとされるXiaomiの次世代SoCについては、いくつかの情報が錯綜している。
2024年末には、北京のテレビ局がXiaomiによる3nmプロセスを用いたスマートフォン向けSoCの「テープアウト」(設計が完了し、製造工程に入る段階)成功を報じた。これは、業界最先端の微細加工技術を用いた高性能チップへの期待を高めるものだった。
だが、より現実的なステップとして、いきなり3nmに行くのではなく、まず4nmプロセスを用いたSoCが登場する可能性が示唆されている。最先端の3nmプロセスでの製造は非常に高コストであり、まず4nmチップで量産プロセスや設計の最適化に関する知見を深めることが、将来的な3nmチップの成功に向けた合理的な戦略と見られているからだ。巨額の投資が必要となるSoC開発において、段階的なアプローチを取ることは理にかなっていると言えるだろう。
Xiaomiが設計しているチップの性能は、Qualcommの2世代前のハイエンドチップである「Snapdragon 8 Gen 1」(2021年発表)に匹敵するレベルになると予想されている。また、CPUコアにはArmの既存設計を利用し、完全な独自コア設計ではないとも伝えられている。
この新しい自社開発SoCは、早ければ2025年前半に発表され、「Xiaomi 15S Pro」といった次期フラッグシップモデルに初めて搭載されるのではないか、という噂も流れている。Xiaomiの共同創業者である林斌(Lin Bin)氏も、SNS上でXiaomi 15S Proの存在を認めており、期待が高まっている。さらに、TechPowerUpは、Xiaomiが開発中のSoCシリーズに「Xuanjie」という名称が付与される可能性があるとも報じている。
自社開発の背景とチップ業界の状況
Xiaomiがチップの自社開発に本腰を入れる背景には、複数の要因がある。
まず、QualcommやMediaTekなどの主要チップメーカーは、より高度な製造プロセス技術への移行を進めており、その結果チップセットの価格は上昇の一途をたどっている。5nmや3nmといった最先端プロセスへの移行には莫大な投資が必要で、その費用はチップ価格に反映される。Xiaomiのようなスマートフォンメーカーはこの価格プレミアムを支払わざるを得ない状況だ。
また、近年の米中貿易摩擦により、中国企業は技術的自立の必要性を強く認識している。Huaweiの例に見られるように、米国の制裁によって先端チップへのアクセスが制限される可能性は、中国テック企業にとって大きなリスク要因だ。Xiaomiはこうした地政学的リスクを軽減するためにも、チップの自社開発を急いでいると考えられる。
自社チップの開発は、外部依存を減らし、長期的にはコスト削減につながる。さらに、ハードウェアとソフトウェアの緊密な統合による製品差別化も実現できる。AppleのAシリーズやMシリーズチップの成功は、こうした垂直統合がもたらす競争優位性を明確に示している。Appleはチップの性能だけでなく、ソフトウェアとの最適化により優れた電力効率とユーザー体験を実現している。
業界への影響と今後の展望
Xiaomiが自社チップの開発に成功すれば、スマートフォン業界の勢力図に大きな変化をもたらす可能性がある。現在、モバイル用SoC市場はQualcomm、MediaTek、Appleなど一部の企業が支配している。Xiaomiの参入により競争が激化し、イノベーションが促進される可能性がある。
特に中国市場では、Xiaomiの自社チップ搭載端末が「国産技術」として評価され、シェア拡大につながるだろう。中国政府の技術自立政策とも合致するこの動きは、地政学的な観点からも注目される。Huaweiが米国の制裁によって苦境に立たされる中、Xiaomiは中国スマートフォン市場での主導権を握るチャンスを得ている。
ただし、初期の自社チップが最新のQualcommやMediaTekのフラッグシップチップと同等の性能を発揮できるかは不透明だ。チップ設計の専門知識と経験は一朝一夕に培えるものではない。自社チップの開発と改良には数年を要する可能性がある。その間もXiaomiは主力モデルには引き続き外部チップを採用する可能性が高い。
また、チップ製造に関しては、XiaomiはTSMCなどの外部ファウンドリ(半導体製造受託企業)に依存せざるを得ない。半導体製造は極めて資本集約的な産業であり、製造能力の確保も重要な課題となるだろう。
Xiaomiの自社チップ開発の進捗と成果は、今後数年間のスマートフォン市場の動向を占う重要な指標となる。成功すれば、他のスマートフォンメーカーも追随する可能性があり、業界全体の垂直統合が進む契機となるかもしれない。
Sources